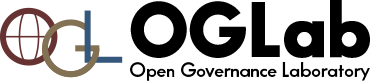ロシアユーラシア
レクチャーシリーズ
ロシアユーラシア研究 第一回
2020年9月26日
ユーラシア近代帝国と現代世界~「帝国論とユーラシア国際関係」
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター 宇山智彦教授
ご講演内容の紹介動画
目次
- 帝国論を論じる意味
- 帝国とは
- 帝国論から国際関係を考えるためのキーワード
- 拡張志向・地位回復志向
- 多様性と階層性
- 大国間の対立・競争・共存
- コラボレーター論
- 公共財の提供・援助と小国のバーゲニング
- 一方的な都合による関与と撤退
- 帝国論からみるロシア
- 世界秩序の変化
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターの宇山といいます。私は中央アジアを中心に中央ユーラシア地域の歴史、主に近代史ですね、それと現代政治をずっと研究してきた人間で、歴史的な見方を現在を見る目にも生かすことを心掛けています。その意味するところは、単に、例えば、ロシアは昔からこういう国だったとか、中央アジアは昔からこうだったから、今もそうなんだとかいうことではなく、歴史を見る際のものの見方、あるいは、多少、理論的な見方を現在に適用する、あるいは、当てはまらない場合は、なぜ当てはまらないかを考えるということをやってきたつもりです。きょうは、お話しさせていただく機会をいただいて、大変、ありがたいのですが、最初の 3 回を担当するという大変重い責任を負うことになりまして、最初は帝国論と国際関係ということでお話しさせていただくことになりました1。
きょうのお話では、中央アジアに関しては、実はほとんど具体的なことは、話はしません。どちらかというと、理論的、抽象的なお話になるかと思います。実務家のかたがたもいらっしゃるところで、場違いかもしれないのですが、ロシアなり、ユーラシアなりを理解する際に、単にロシア、ユーラシアだけを見ていれば分かるというものではない。多少、理論的な視点、あるいは、比較の視点が必要ではないかということで、理論的な視角として、帝国論というものを紹介させていただきたいと思っております。きょうのお話のベースになるものとして、画面の左側に映っているかと思いますが、2016 年に出しました、『ユーラシア近代帝国と現代世界』という本があります。これは、われわれのセンターでやっていた大きなプロジェクトで、ロシア、中国、インド の三つの大国を、歴史、現在、それから文化など、さまざまの面から比較しようというプロジェクトの成果の 6 冊のうちの 1 冊です。
それから、ロシアに関しては、ロシアの国際関係の特徴について、主に歴史の話なんですが、現在にも少し言及した論文を、大阪大学の秋田茂先生が編集した『グローバル化の世界史』という本に書かせていただきました。これについても後で触れることになるかと思います。

帝国論を論じる意味
お話に入っていきますが、帝国論というもの、そういう言葉をどのくらいお聞きになったことがあるか分かりませんが、歴史研究や国際政治の研究の中で、2000 年代、2010 年代に流行したものです。その流行した背景、文脈にはいくつかのものがあります。一つは、歴史研究の中で帝国というものを見直すということで、これは、次回、民族問題などの話をする際に、そのベースとしてお話しすることになるかと思います。きょうの話にも、実は、いろいろな形で入ってはいるのですが、次回、もう少しまとめてお話ししたいと思います。
2 番目は思想的な文脈で、これは特に 20 世紀の終わりのほうに、国民国家というものが、もう行き詰まっているのではないかということで、それに代わるもの、あるいは、国民国家を相対化して考えるために帝国というものを考えようという議論。それから、グローバル化が進んで、もはや、いろいろな国の政府が権力を持つというよりは、世界にまたがるネットワーク状の権力として新しい帝国が成立しているのではないかという、これも一時、はやったネグリとハートの議論ですね。こういったものがあったのですが、2010 年代の特に半ば以降になると、国家間、大国間の競争が激しくなっていって、どうも、国家を超えるという意味での帝国がアクチュアリティーを持つというのとは、かなり違う状況になってきたと思います。
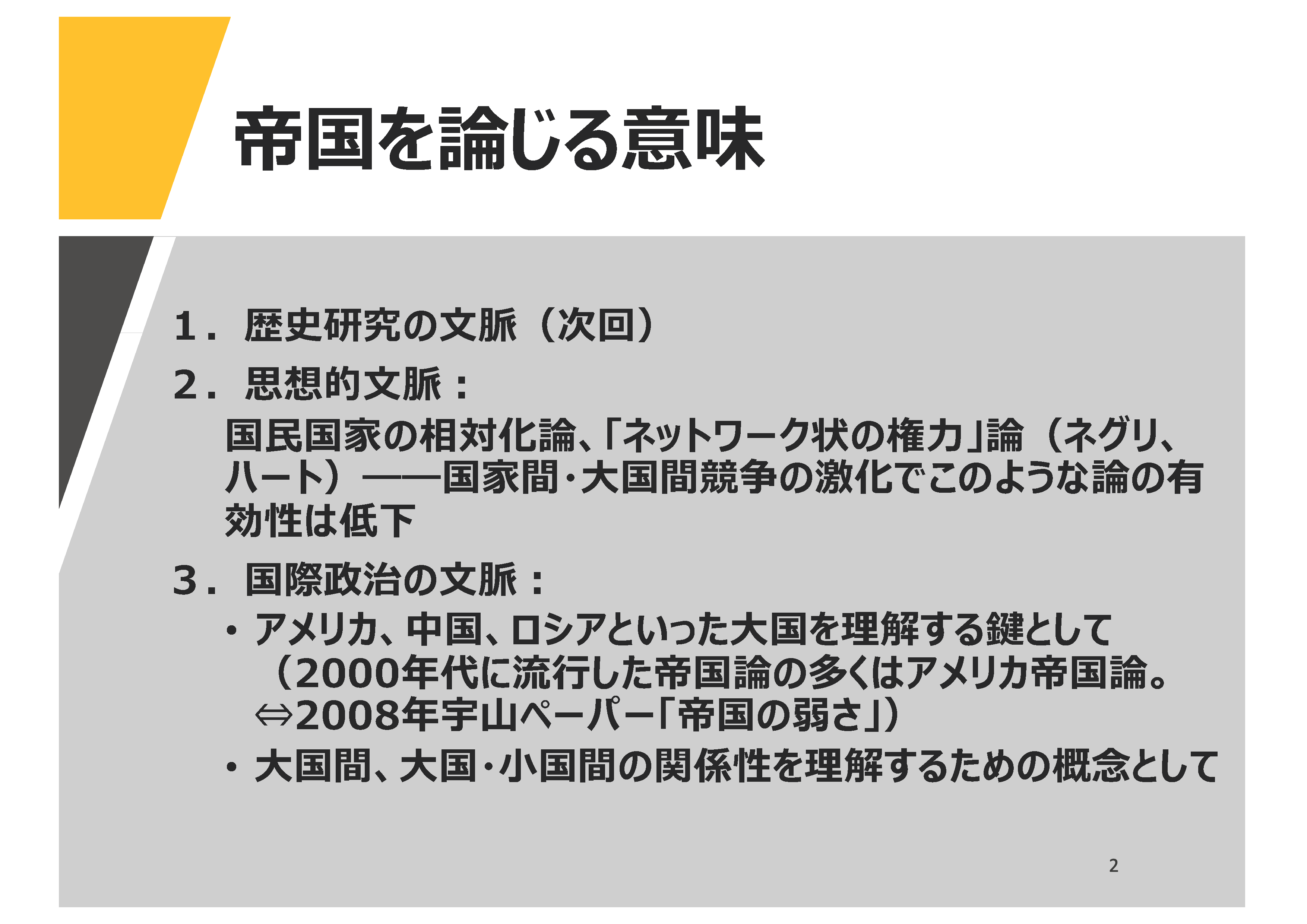
三つ目は、国際政治の文脈で、それも二つの方向性に分けられると思います。一つは、アメリカ、中国、ロシアといった、具体的な大国を理解する鍵として、アメリカ帝国論、あるいは、中国を帝国として見る、ロシアを帝国として見るというアプローチがあります。特に帝国論が一番流行した 2000 年代には、アメリカ帝国論というものが非常に注目されました。特に 9.11 事件以降、アメリカが唯一の超大国としてテロと戦い、民主主義を世界に広めていくという考え方がはやったわけですね。今、そういったものを読み返すと、非常に時代を感じるところがあります。
私自身は、当時から、そんなにアメリカばかり見ていてもしょうがない。アメリカは、そんなに万能ではないし、他の大国のことをもっと考えないといけないというふうに思いまして、2008 年に「帝国の弱さ」というひねくれたタイトルのペーパーを書きました。これは、あるシンポジウムで発表して、活字になったのは少し後、2012 年ですが、スラブ・ユーラシア研究センターのサイトに載っていますので関心ある方は検索して見てください。私もついさっき読み返して、まだ、あまり考え方は変わらないなということを発見して、その後、12 年間、帝国については随分研究をしたつもりなんですが、どうも見方が進化してないなというふうに、ちょっとがっかりしたのですが、同時に歴史に立脚して、現在を見る見方というのは、そう時流に流されずに、変わらずに存在することができるんだということも確認できたような気がします。
帝国とは
それからもう一つは、一つの大国というよりは、大国間、あるいは、大国と小国の間の関係性を理解するための概念として帝国を使うというものです。きょうの話は、その前者、具体的な大国の話にも、特にロシアについて触れますけれども、どちらかといえば、関係性を理解する概念としての帝国が中心になるかと思います。帝国というのは、かなり伸縮自在といいますか、見方によっては捉えどころのない言葉で、これを使って議論すると、常に定義論争になってしまいます。ただ、定義論争というのは往々にして、非常に不毛になってしまいますので、私としては深入りしたくないところなのですが、『ユーラシア近代帝国と現代世界』という本で は、一応、暫定的な定義として、いくつかのことを書きました。それを改めてまとめますと、一つには相対的に大国であるということと、対外的に勢力圏を拡張する志向を持つということですね。
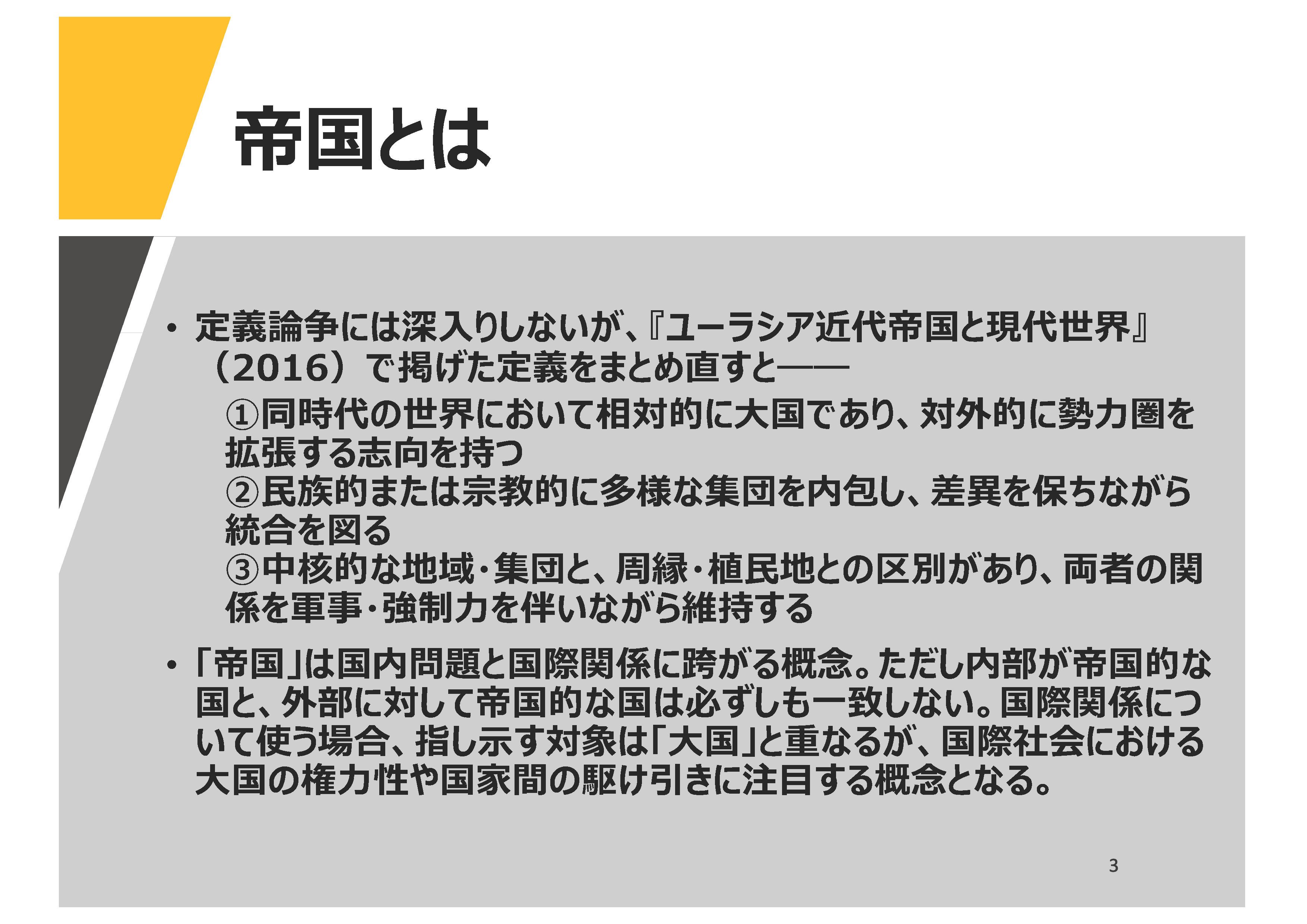
それから、2 番目は民族的、または宗教的に多様な集団を含む。それらの差異、違いを保ちながら統合を図っていくということ。それから 3 番目に、中核的な地域や集団と、周辺ないし植民地との区別があって、その両者の関係を軍事力、あるいは、強制力を伴いながら維持するということです。この定義 は、どちらかといえば帝国の中に、より注目するものですが、帝国というのは、しばしば境界線が柔軟である、変化するということもあって、国内問題と国際関係にまたがる概念として帝国というものを使うことが多いです。ある意味では、帝国の中のことを考えるための枠組みを、帝国の外、国際関係を考えることに応用できるということですね。ただ、内部が帝国的な国と、外部に対して帝国的な国は、必ずしも一致しないということは、断り書きとして付けておく必要があって、特にアメリカ帝国論というような場合は、外部に対する行動にもっぱら注目しているわけですね。国際関係について帝国という言葉を使う場合は、具体的に指し示す対象としては大国というものと基本的には重なるのですが、ただ単に大国ということだけではなく、大国が持つ権力性であるとか、国家間の駆け引きというものに注目する概念として帝国が使われるわけです。
帝国論から国際関係を考えるためのキーワード
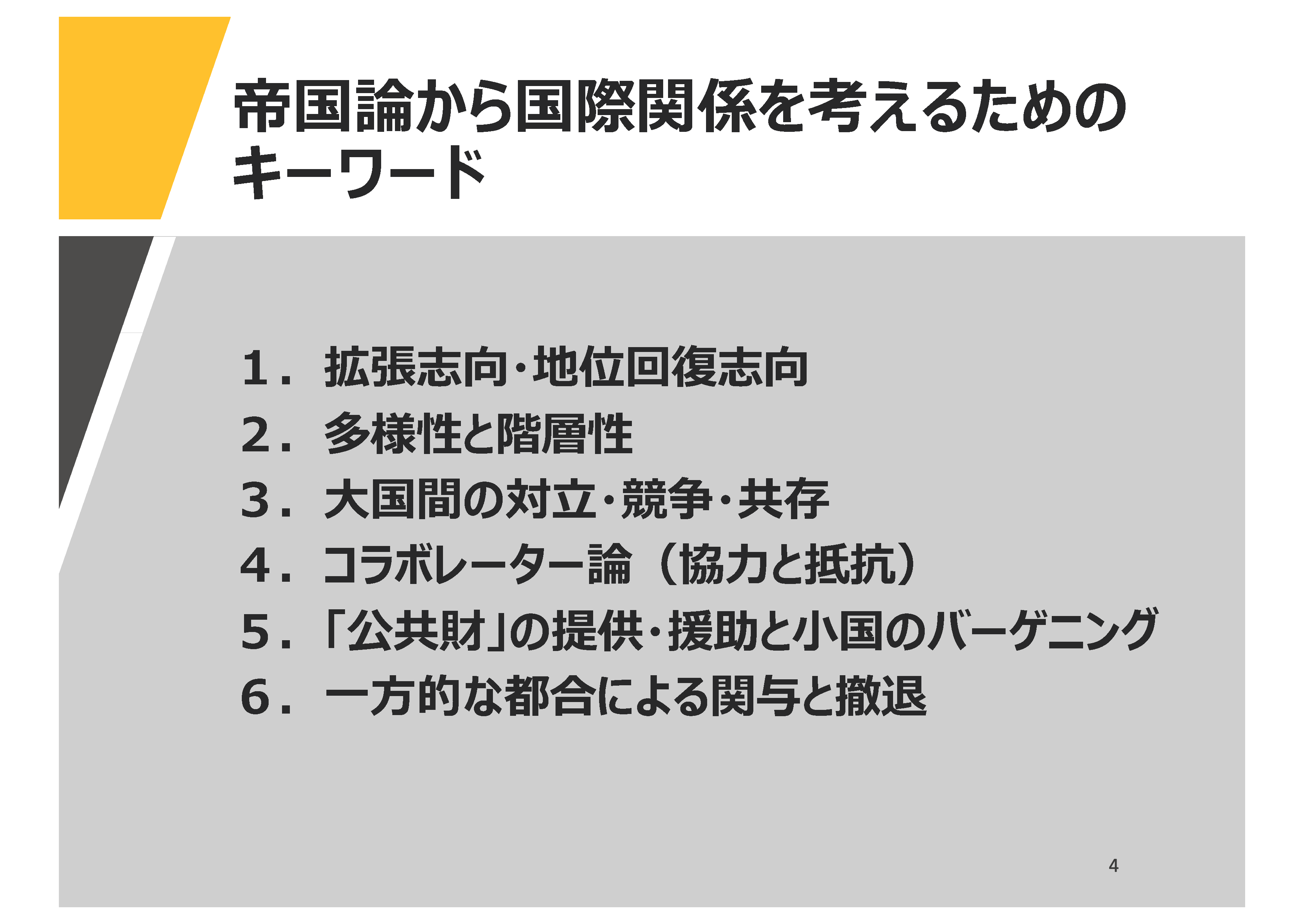
帝国論から国際関係を考える場合には、どういうキーワードがあるだろうかということで並べてみたのが、この画面です。社会科学的な概念であれば、もっと図式的にクリアにしたりできると思うのですが、歴史から出発した議論というのは、大体、そこまでクリアに図式化しない。むしろ図式化を嫌うようなところがありますので、ちょっと雑然としているかと思いますが、拡張志向・地位回復志向、多様性と階層性、大国間の対立・競争・共存、コラボレーター論、それから、公共財とバーゲニングのお話、また、一方的な都合による関与と撤退ということで、それぞれについてお話をしていきます。帝国というのは、拡張主義的であるということは、よく言われるわけですが、何を拡張させるのかということで、領土を拡大させる場合と、公式の領土ではないんだけれども、影響力を持つ範囲、あるいは、勢力圏を拡大させるという場合があります。
これもイギリスの歴史家たちが提案した用語ですが、領土の広い帝国というのは、公式帝国であり、影響力や勢力圏を広げようとする帝国は、非公式帝国と言われます。植民地拡張の華やかなりし頃は、公式帝国の拡大も目立っていたわけですが、領土以外のところにも影響力を広げようとすることは、歴史上、常にありましたし、現在の世界では、領土の拡大ということは、そう簡単にはできないですので、現在の国際関係について語る帝国というのは、大体が非公式帝国を念頭に置いています。ただし、領土の問題が重要でなくなったわけではなく、ロシアにとってのクリミアであるとか、中国にとっての東シナ海、南シナ海の島々であるとか、面積的にはかなり小さいところの領土であっても、大国の威信にとっては重要であるという場合があります。
拡張志向・地位回復志向
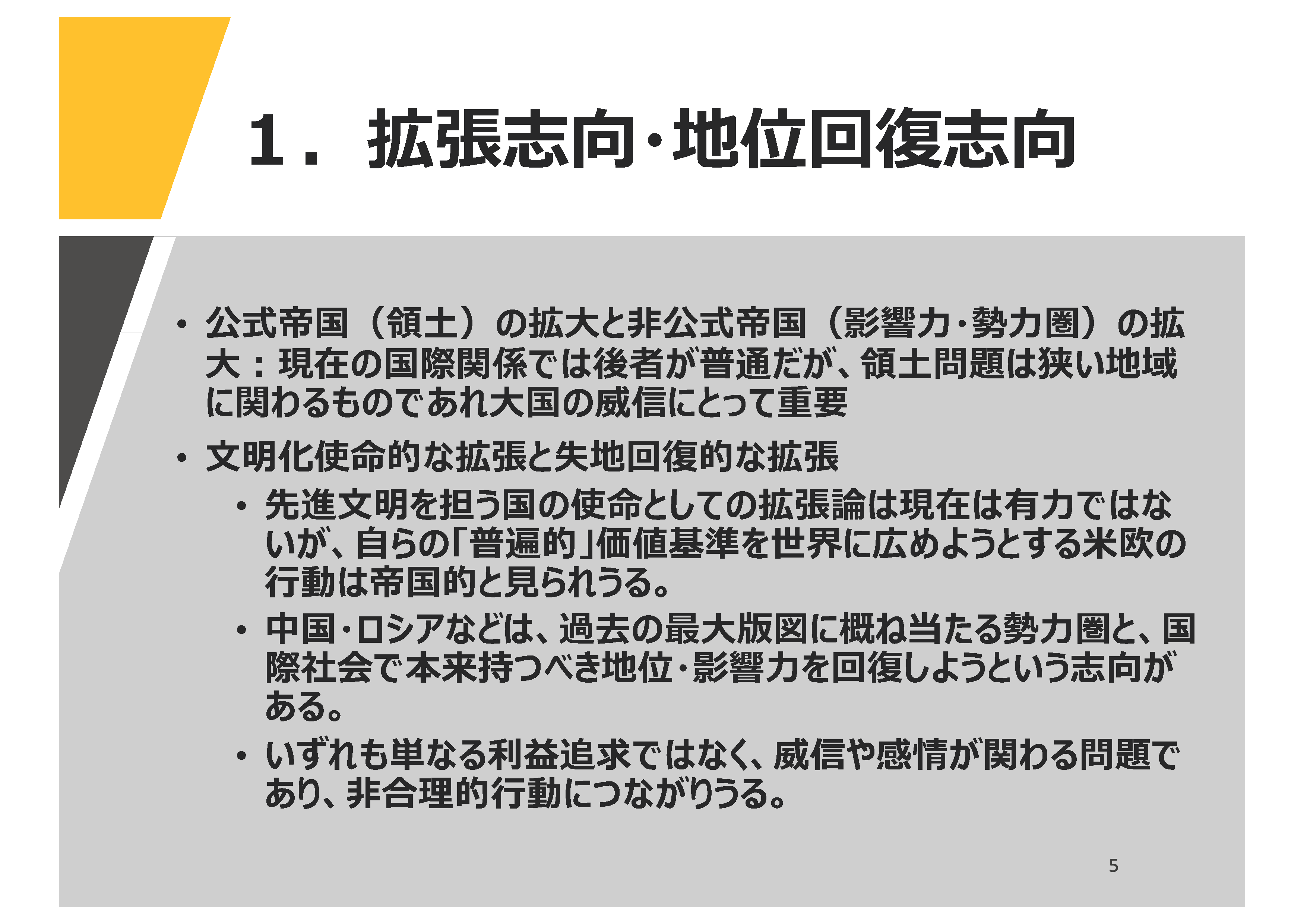
また、どういう動機で拡張するのかということで考えると、これも 2 種類。文明化使命的な拡張と、失地回復的な拡張があると思います。19 世紀、ヨーロッパの帝国は、多くの場合、文明化の使命なり、あるいは、アメリカであれば、もっと広い意味でのマニフェストデスティニーなり、何らかの使命を持って拡大するのだというふうに主張していたわけです。これも現在では、そういうことを正面から主張することは少なくなっていますが、自分たちの価値基準を世界に広めようとする行動は、今でもしばしば見られるところです。それは特に、アメリカ、あるいは、ヨーロッパには顕著だと思います。他方、中国やロシアを典型として、過去にはもっと広い領土を持っていた国は、その過去の最大版図に、大体、対応するような範囲を勢力圏として回復したいという志向を持ちがちです。それは、単に地理的な勢力圏というだけではなく、自分たちが国際社会で、本来、持つべき地位や影響力を回復しようという考え方でもあります。いずれの場合も、単に経済的な利益だとか、領土に含まれる資源だとかいうものを追求して拡大しようというだけではない。むしろ、威信とか感情が関わる問題であって、それ故に非合理的な行動を帝国的な国々がとることにつながっています。
多様性と階層性
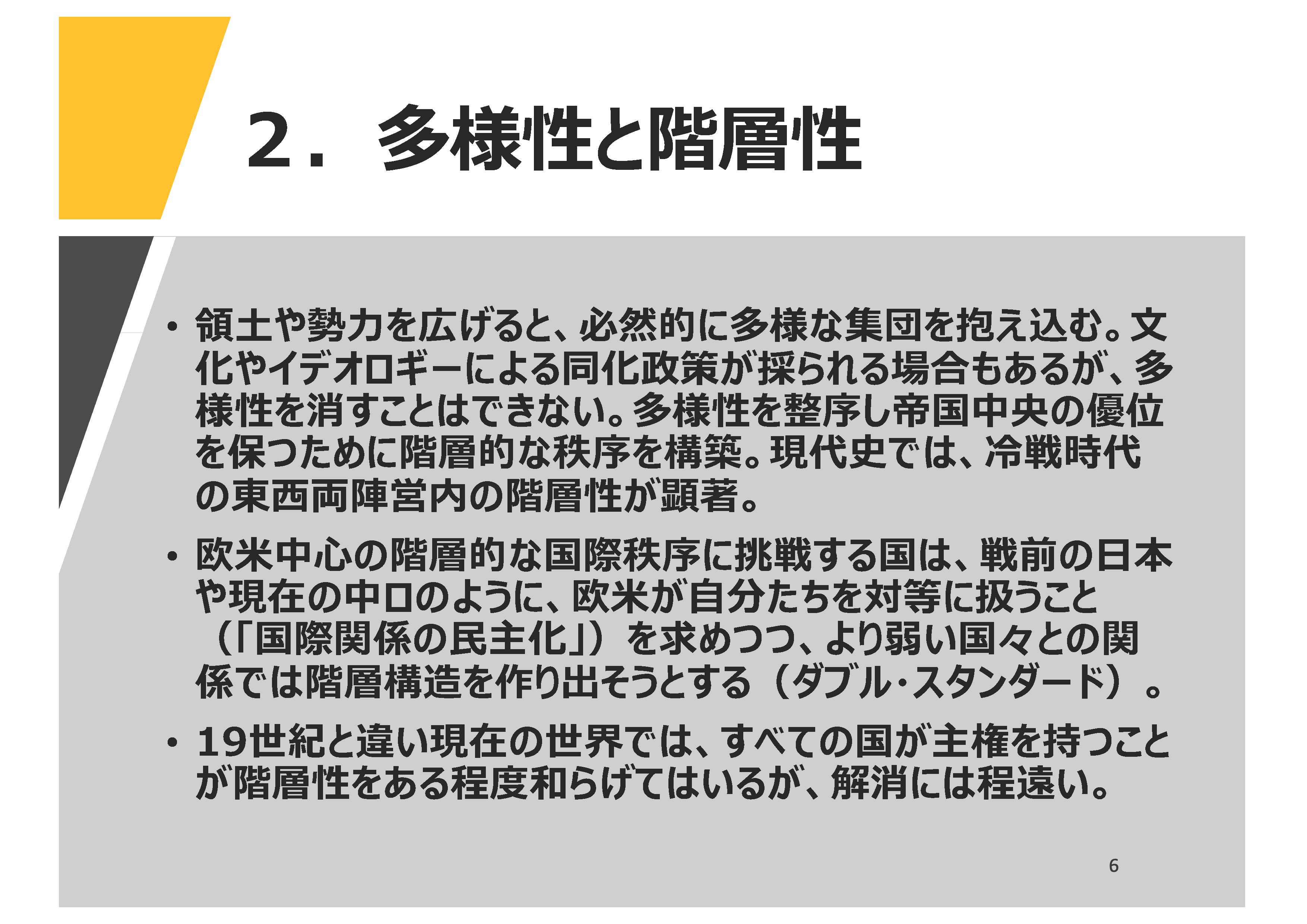
それから、2 番目のキーワード、多様性と階層性です が、領土や勢力を広げると、必然的に多様な集団を中に抱え込むことになります。これについても、歴史研究の中で同化政策なのか、それとも、むしろ差異を操作する政策が多かったのかということが、たくさん議論されてきました。さまざまな文化装置、あるいは、イデオロギーによって同化を進めようという例は多々ありますが、それでも決して多様性は消えません。国際関係史でいえば、ソ連が共産主義諸国を衛星国としてイデオロギー統制を進めたけれども、決して、それによって、例えば、東ヨーロッパ諸国とか、モンゴルとかがソ連と同じような国になったとは言えないわけです。
そういった多様性を抱えた中で、中央の優位を保つために階層的な秩序を構築する。冷戦時代には、東西両陣営で、それぞれソ連とアメリカをトップとする階層構造がつくられたわけです。現在では、そういった嘗ての二つの陣営というものは消えて、後でお話しするように、非常に複雑な構図になってきていますが、しかし、基本としては欧米中心の階層的な国際秩序というものが存在する。それに挑戦する国々は、戦前の日本もそうでしたし、現在の中国、ロシアもそうですが、欧米が自分たちを対等に扱うことを求めます。特に中国は、国際関係の民主化ということを唱えてきました。
しかし、そういった国々自身も、より弱い国々との関係では、自分たち大国のほうが、当然、発言権が大きいのだということで、階層構造をつくり出そうとする。そういうダブルスタンダードが、この既存の秩序に挑戦する大国にはつきものです。こういった階層構造の中で、中小規模の国、特に小国は、行動の自由に何らかの制限が現れてしまいますが、ただ、19 世紀と違って現在の世界では、建前として全ての国は主権を持っているということで、そういった階層性が、ある程度、和らげられていますけれども、しかし、決して、大国と小国の区別は消えていない。ですから、この階層性という問題は、現在の国際関係を考える上でも非常に重要な問題である。身近なところで言えば、日米関係などというのは、明らかに階層構造を持っているわけですね。
大国間の対立・競争・共存
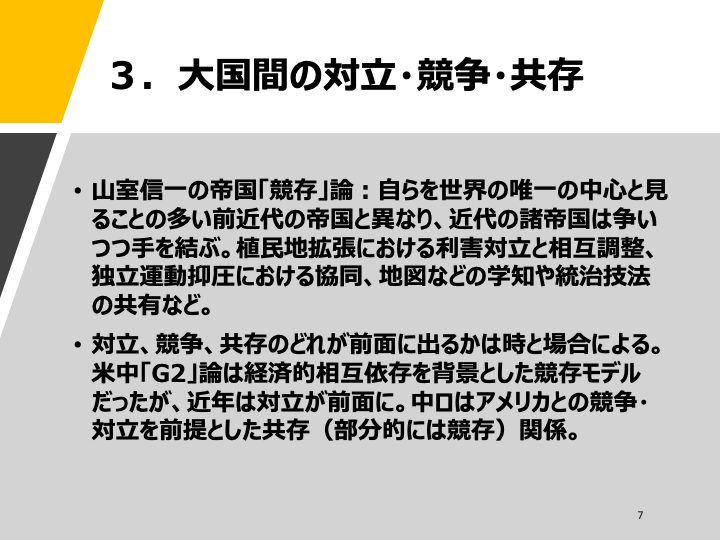
それから 3 番目に大国間の関係というものが、対立、競争、共存という三つの面を持っているということです。これも歴史研究の中から出てきた議論で、日本帝国の研究で有名な山室信一先生が、近代帝国の競存論――共存の共を競争の競に変えたものですね――というものを唱えておられます。前近代の帝国、特に古代ローマ帝国であるとか、中華帝国といったものは、現実はどうかは別として、理念の上で、自らが世界の唯一の中心であると考えていたわけですが、近代の帝国は、そうは簡単に唱えることができない。他にもいろいろな帝国がある中で、一方では争い、しかし、どこかで手を結ぶ。特にヨーロッパの帝国であれば、お互いに争うんだけれども、しかし、ヨーロッパ中心の国際秩序で植民地を、それぞれが獲得していくという構造については理解を共有していたわけで、ですか ら、対立しつつも、どこかで利害の調整をする。そのためのいろいろな技術や知識も共有するという議論です。
この対立、競争、共存のどれが前面に出るかは、時と場合によりますが、現在の世界について言えば、一時、かなりよく唱えられた、アメリカと中国の G2 という議論。これは、アメリカと中国が覇権を争うんだけれども、しかし、経済的には相互依存しているから、競争と共存が合わさった競存のモデルとして捉えられたわけですが、しかし、近年は対立のほうがずっと前面に出てきている状態です。中国とロシアの関係については、これも、もし時間があれば、後で議論したいと思いますが、特に日本では、中国とロシアは、一見、仲良くしているけれども、実は仲が悪いんだという見方が最近まで、かなり力を持っていました。しかし実際には両方の国がアメリカとの競争ないし対立を前提としていて、中国とロシアとしては、全ての面で利害を共有するわけでは、当然、ないけれども、基本的には共存していこうという関係になっていると思います。
コラボレーター論
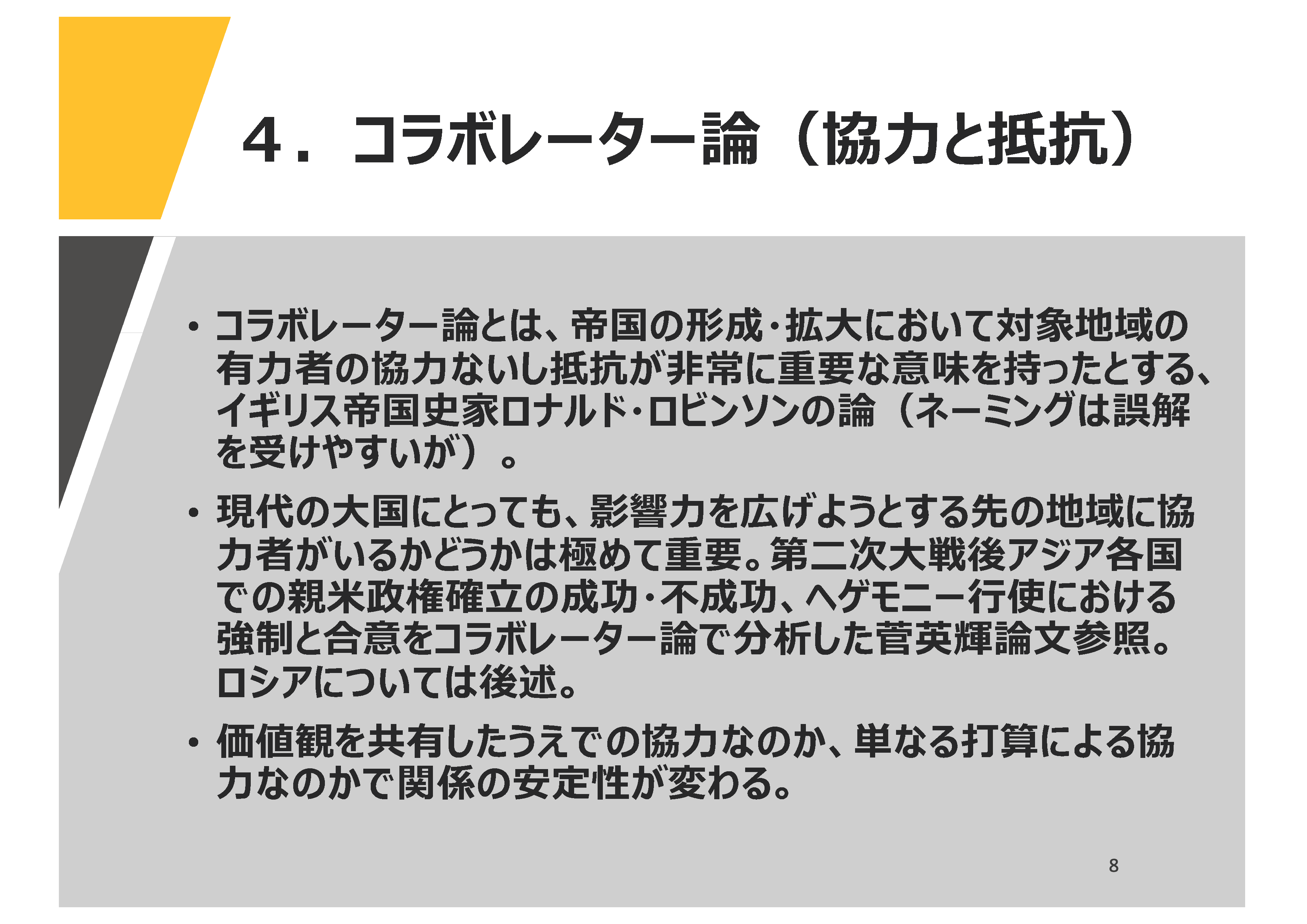
次に、コラボレーター論という、恐らく多くの方には見慣れない言葉を出しました が、これはイギリス帝国史研究者として、かつて活躍していたロビンソンという人の議論で、ロビンソンは、イギリス帝国をはじめ、ヨーロッパ諸帝国が拡大する際に、拡大していく先の地域の有力者が協力するのか抵抗するのかというのが、帝国の拡大を大きく左右したし、帝国そのものの性格にも大きな影響を与えたんだと。つまり、帝国というのは中心から外への作用というだけではなく、周辺から中心への作用を見なければいけないんだという議論です。ですから、協力だけではなく、抵抗の側面も見ていますし、コラボレーターという言葉が、不幸なことに特にヨーロッパの大陸のほうの歴史では、ナチズムへの協力という特定の意味を持ってしまうので、この議論は非常に誤解されやすいんですが、中身を理解すれば十分にあり得る、そして、適用範囲の広い議論であるということが分かるかと思います。
これは、どちらかといえば、19 世紀の植民地を持った帝国、あるいは、植民地以外のところにも影響力を持った非公式帝国を念頭に置いているのですが、20 世紀、あるいは、現在の大国を見る際にも、この議論は有効になると思います。最初にご紹介した『ユーラシア近代帝国と現代世界』という本では、菅英輝先生が、アメリカ帝国を論じる際に第 2 次世界大戦後にアジア各国で親米政権を確立するという方針が、どこで成功し、どこで成功しなかったのか。なかなかうまくいかないときに、強制的にヘゲモニーを行使するのか、あるいは、何とか合意をとりつけるのかということについて、コラボレーター論を応用されています。
具体的に言えば、日本、特に吉田茂政権は、親米政権として確立したけれども、韓国の李承晩政権 は、親米政権の側面も持ちながら、同時に強烈なナショナリズムを主張して、非常にてこずったとか、中国であれば、アメリカが後押しした国民党政権がうまくいかなくなってしまったとかいうことを、アメリカの政策と現地の事情の相互作用として語れるということです。ロシアについては、後で少し触れたいと思います。吉田政権が親米政権として、割合、スムーズに確立したけれども、他のアジア諸国ではそこまでではなかったということの一つの原因は、大国側の価値観を小国ないし周辺地域の統治者、有力者が共有しているかどうかということがあるわけで、価値観を共有しているのか、それとも、単なる打算による協力なのかで関係の安定性が変わるということも、大国と協力者という話をするときには重要なポイントだと思います。
公共財の提供・援助と小国のバーゲニング
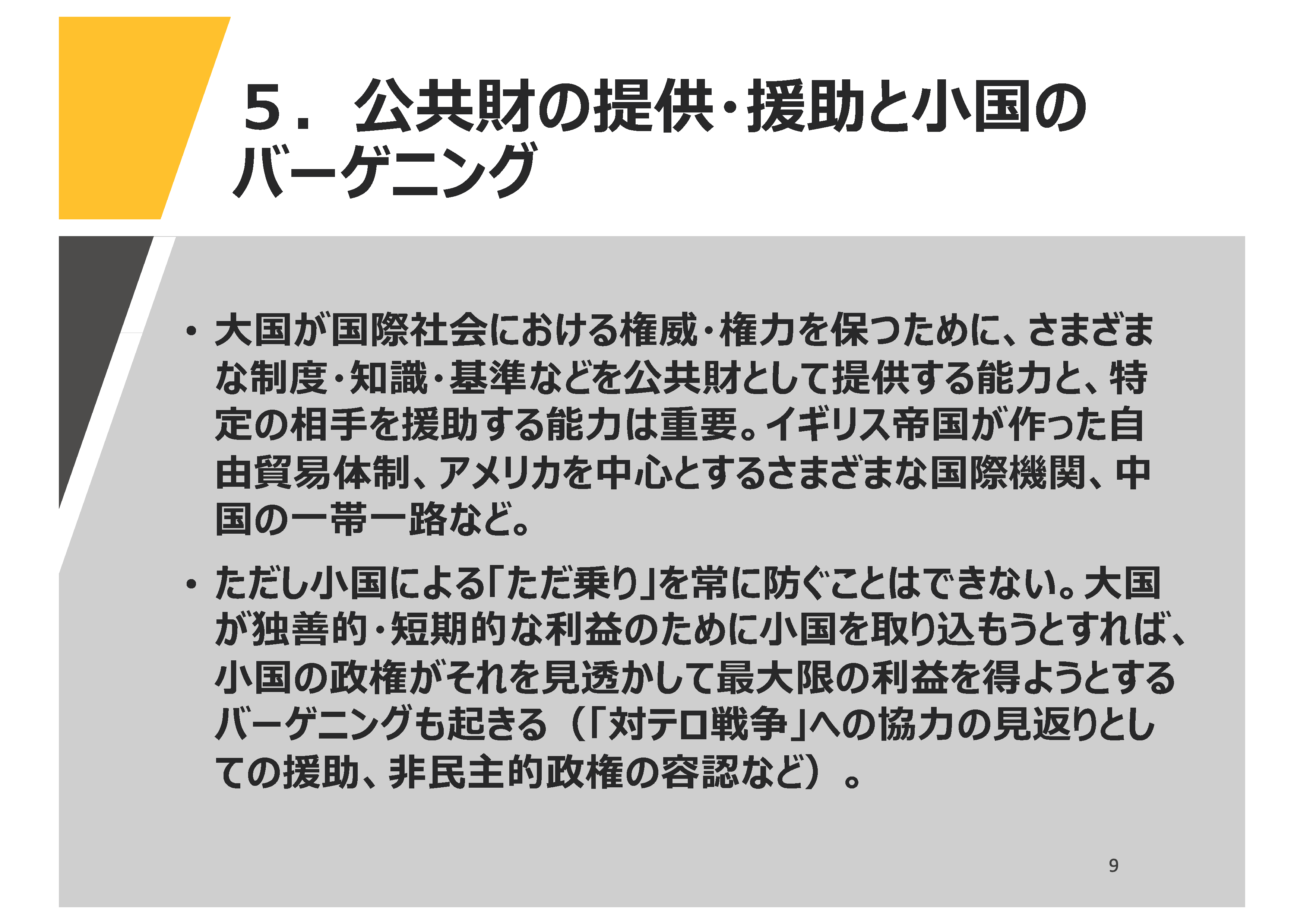
それから 5 番目に、いわゆる、国際公共財についての話ですが、大国が国際社会における権威や権力を保つためには、単に軍事力とか、経済力だけではなく て、さまざまな制度や知識、基準などを公共財として提供する能力が重要ではないかという、これも最初はイギリス帝国の研究から出てきた話です。つまり、イギリス帝国がつくった自由貿易体制であるとか、いろいろな決済のシステムといったものが、世界的に受け入れられることがイギリスの世界の中心としての地位を保証していたという話です。
アメリカの場合も、今のトランプ政権は全く違う姿勢ですが、かつては、さまざまな国際機関の設立、運営の中心になるということに熱心でしたし、それから、特に 20 世紀後半以降は、国際公共財の提供というだけではなく、特定の相手に対する援助も重要になってきて、アメリカも日本も、それを熱心にやってきたわけです。中国も一帯一路構想で、さまざまな国に対する援助を盛んに行っています。ですから、こういうことが大国の影響力拡大の重要な道具になるわけですが、ただ、そういうものを利用するだけ利用して、大国の言うことは聞かないという小国も、当然、出てきます。
特に大国側が独善的、短期的な利益のために小国を取り込もうとすれば、小国の政権がそれを見透かして最大限の利益を得ようとするバーゲニングの行動も、しばしば見られます。典型的なのは、アメリカが対テロ戦争を唱えたときに、いろいろな国が協力しますといって、その見返りとして、権益や援助を求めたということです。また、冷戦時代から現在に至るまで、アメリカが戦略的な利益のために、どこかの国の政権を味方につけようとして、そうすると、普段は批判しているはずの非民主的な政権を積極的に支えるという、これもダブルスタンダードの行動が起きるということになります。
一方的な都合による関与と撤退
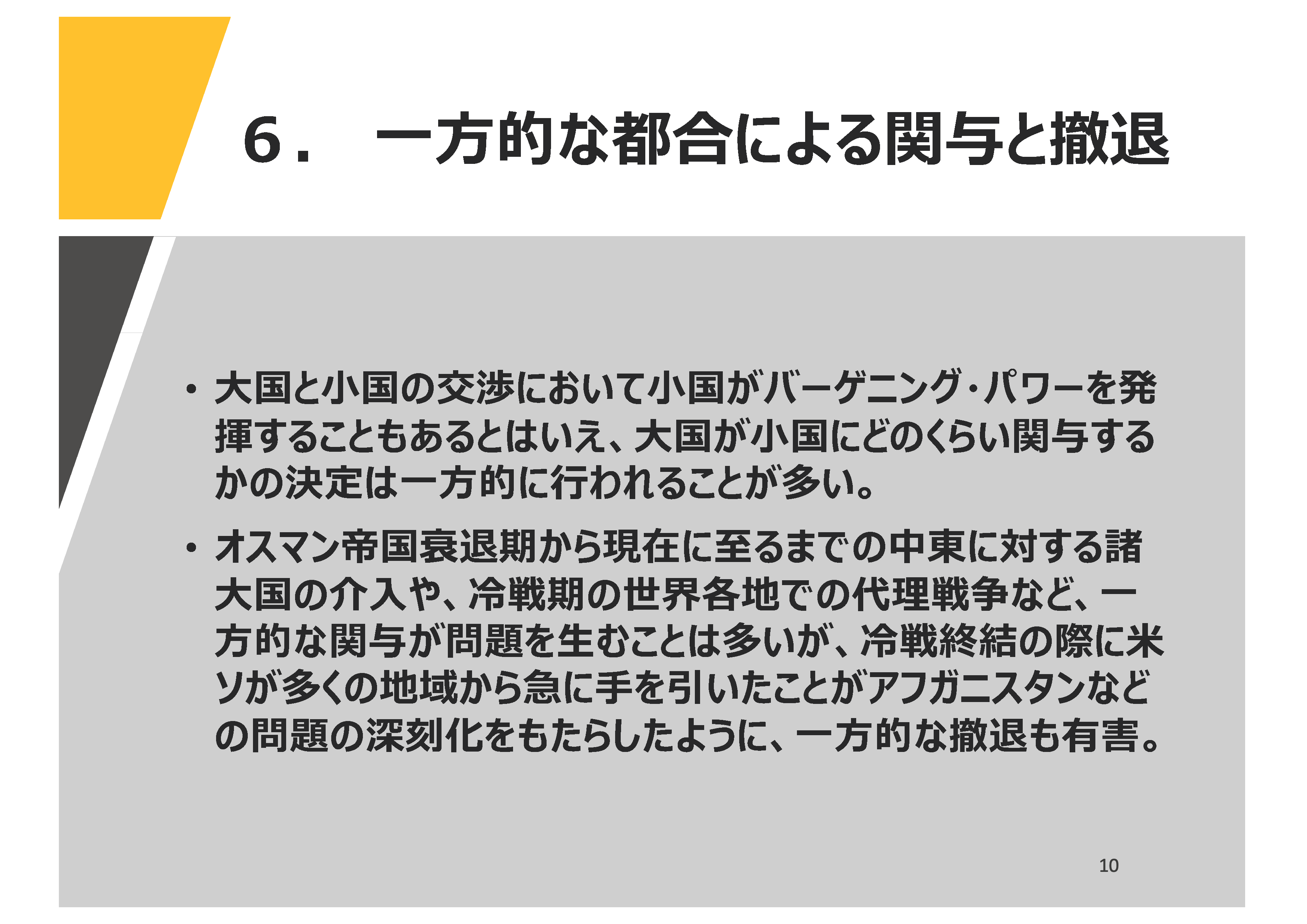
キーワードの最後、一方的な都合による関与と撤退ということですが、大国と小国の関係というのは、今、言いましたように、決して一方的なものではない。小国が自分たちの利益のために大国を振り回すということも、決して珍しくないのですが、ただ、大国が小国にどのくらい関与するかという決定は一方的に行われることが多いと思います。その例が特に集中的に現れるのは中東地域であって、オスマン帝国の衰退期から現在に至るま で、いろいろな国が介入しては、あるときになると突然出ていく。それから、冷戦期には世界各地にアメリカとソ連が介入をして、ときによっては代理戦争が起きるということで、そういった一方的な関与が問題を生むことが多いのですが、しかし同時に、突然撤退することによる影響というのも多々あります。冷戦終結の際に米ソが急に手を引いたことで、アフガニスタンの情勢がさらに泥沼化していったであるとか、あるいは、イラクやシリアへの関与にしても、外部の国、特にアメリカの関与は非常に気まぐれであるということで、一方的な撤退というのも多く問題を生んでいると思います。
帝国論からみるロシア
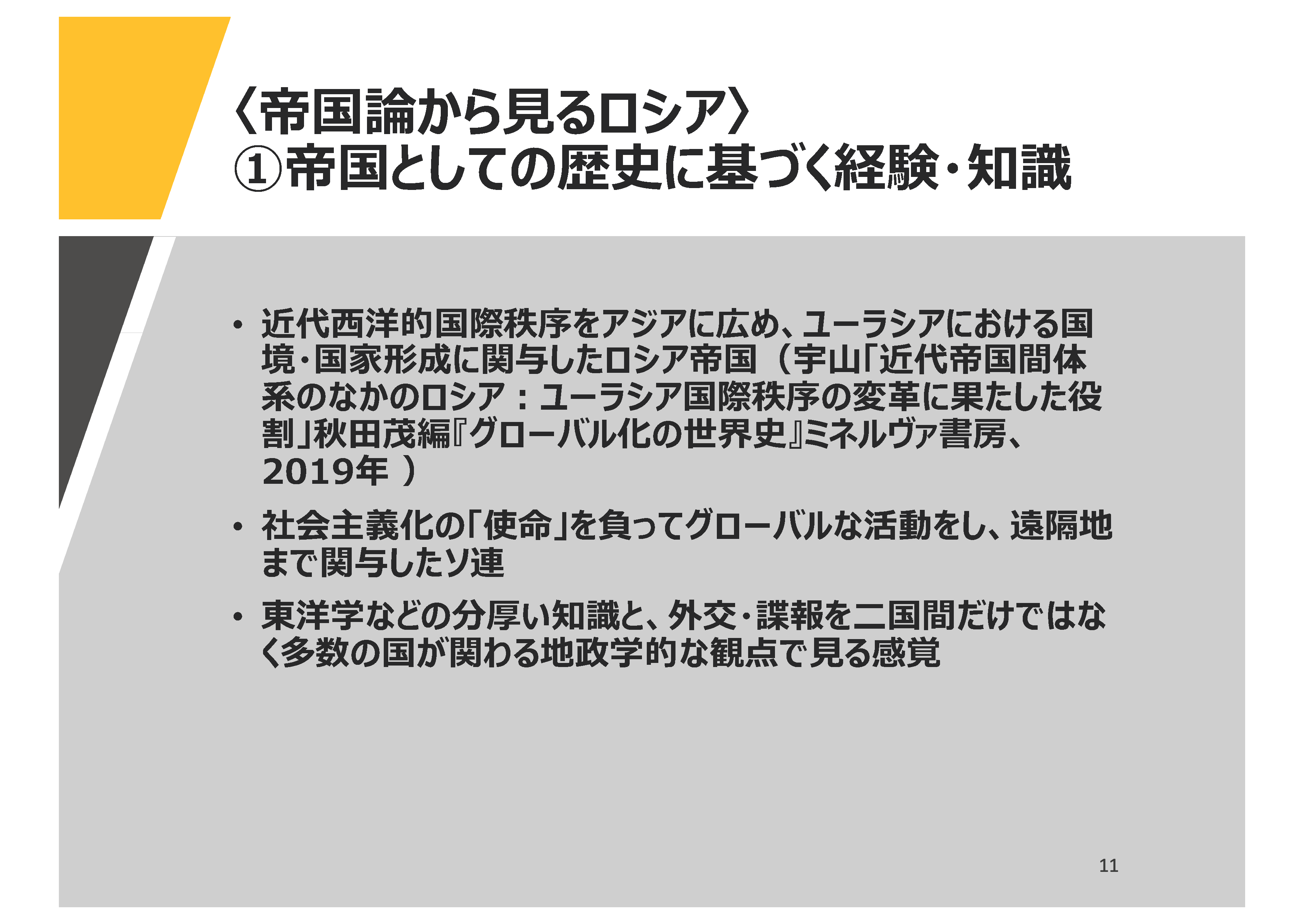
かなり一般論として帝国論的な国際関係ということをお話ししてきましたが、ロシアについて帝国論の見地からはどういうことが言えるのかということを次にお話ししたいと思います。帝国的なロシアというものが、論じる人によっては、西欧、あるいは、欧米と比べて良い帝国であるというふうにいう人もいるし、あるいは、特に欧米でのイメージがそうだと思いますが、非常に粗暴で攻撃的な帝国であるというイメージもあると思いますが、もう少し中立的に見てみると、歴史的な経験、帝国としての経験がかなり豊富な国であるということは否定できないと思います。
最初にご紹介した秋田先生編の本で私が書いたことですが、近代的な国際秩序の形成というのは、大体、西欧諸国が中心になっていたということで語られることが多いのですが、実は中国方面にしても、中央アジア、西アジア方面にしても、国境の形成だとか、部分的には国家の形成が、相当、ロシアが関与して行われたところが大きいと思います。国境の形成もそうですし、国際法を広めるという点で、それから、例えば、戦時国際法の整備においては、世界的にもロシアが果たした役割というのは無視できません。ただ、ロシア帝国の時代には、どちらかといえば隣接する地域といろいろな関係を持つ。遠い地域とはイギリス帝国と違って、あまり密な関係を築くことできない帝国だったわけですが、ソ連の時代になると、世界に社会主義を広めていくという使命、一種の文明化使命を自ら負って、グローバルな活動をする。
特に冷戦期には、アメリカと張り合って、アフリカなど、相当、遠い地域まで影響力を広げていくということで、そこで得られた経験も豊富にあります。シリア問題とか、イラン問題とか、特に中東への関与においては、こうしたソ連時代の経験が相当活用されていると思います。現在のロシアにおいても、東洋学的な分厚い知識が、やはりありますし、特に中央アジア、中東方面の地域については、欧米に劣らない知識を持っている国です。また、同時に、外交とか諜報という問題を 2 国間の問題だけではなく、多数の国が関わる地政学的な問題であるということで捉える感覚が発達していると思います。
日本の場合は、いろんな国に関する知識は、相当高いレベルで持っていると思うのですが、外交を考える際にどちらかといえば、2 国間の関係で考える、あるいは、抽象的な国際社会との関係で考えるということが多い。典型的に現れるのは、ロシアを相手にした領土交渉で、日本としては、ロシアと仲良くすれば、いつか返ってくるというような感覚が出がちですが、ロシアの側は、日本との関係を常にアメリカと絡める、あるいは、中国と絡めるといったことで見ている。そういった感覚は、ロシアは発達しているのではないかと思います。
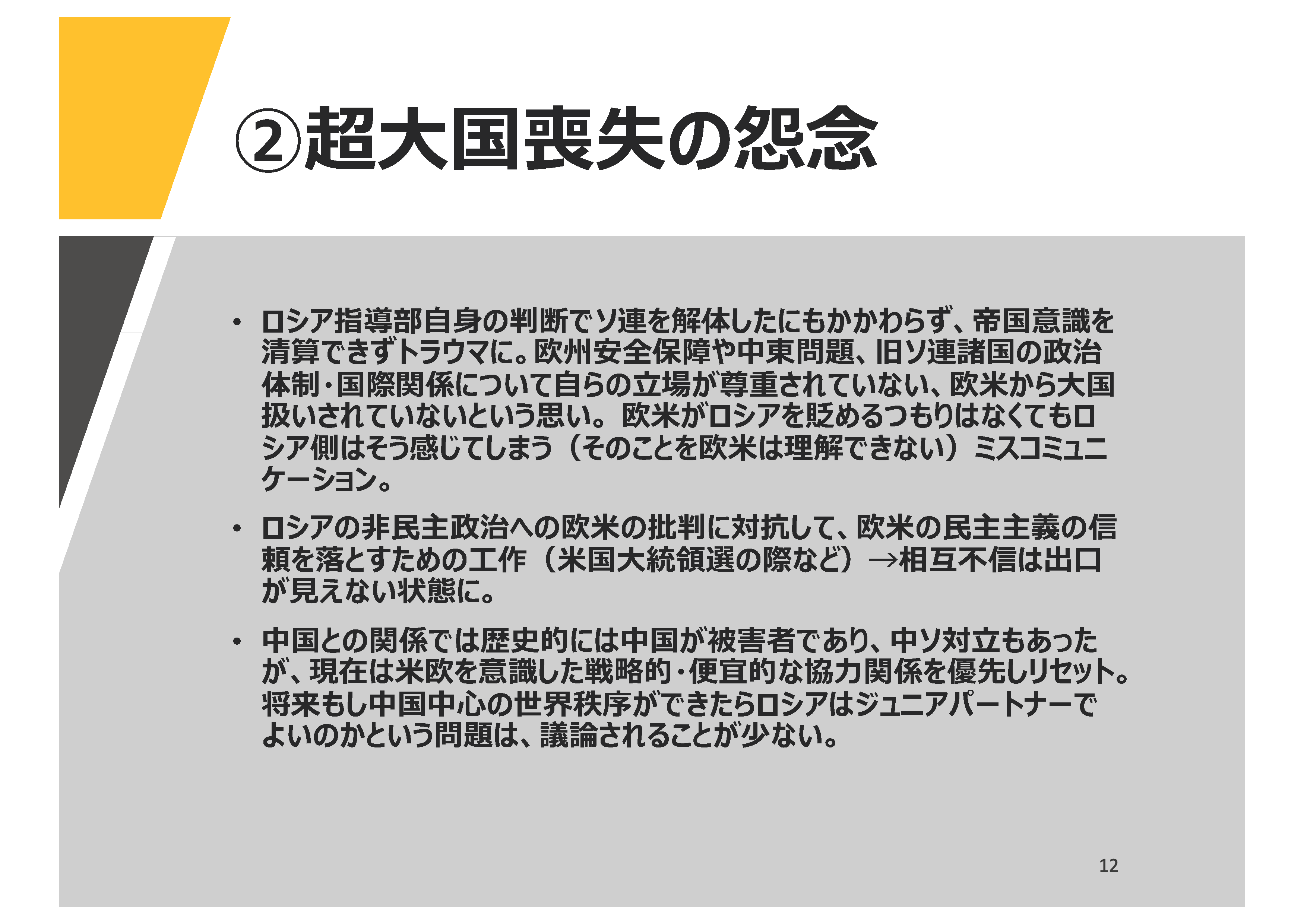
2 番目ですが、最初のほうでお話しした、国際関係において、特に帝国にとって威信とか、感情の問題が重要であるということをお話ししましたが、それがロシアの場合、かなり鮮明に表れていると思います。つまり、かつては超大国ソ連であったのが、その地位を失ってしまったということに対する怨念です。客観的に見れば、ソ連を解体したのは、当時のロシア指導部自身の判断が大きかったのですが、しかし、当時、CIS、独立国家共同体を設立する際には、例えば、共通の軍隊の保持なども想定していたわけで、そんなに一気にソ連的なものがなくなると思っていなかった面があります。それが結局は、ばらばらに解体してロシアの独占的な影響圏ではなくなってしまったということもあって、しかし、ロシアは本来、大きな帝国であるはずだという帝国意識を清算できない。その意識と現実の違いでトラウマが生じてしまったといってよいと思います。
それは、旧ソ連地域内部の問題というだけではなく、むしろ欧米との関係で、NATO の東方拡大を典型とする、ヨーロッパの安全保障の問題、あるいは、中東の問題、それから、旧ソ連諸国の問題について、ロシアの立場が尊重されていないという思いがあります。一言で言えば、欧米から大国扱いされていないという感覚です。NATO の東方拡大にしても、実際には東ヨーロッパ諸国自身が、それを求めたということがありますし、また、西ヨーロッパやアメリカの側が、最初からずっと計画的に NATO 東方拡大を進めていたというわけではないのですが、ロシアから見ると欧米の側に悪意があって、ロシアを敵視して NATO を東に広げていったという感覚になってしまう。
つまり、欧米が必ずしもロシアをおとしめるつもりがない場合でも、ロシア側はそう感じてしまうし、そういう複雑な感情を欧米側は理解できないというミスコミュニケーションが生じているところがあります。そういう状態にロシア側がいら立って、特にロシアの政治が民主的ではないということに対する批判に対抗するということで、では欧米の民主主義の信頼を落としてしまえということで、アメリカ大統領選挙の際などにいろいろな工作を行ったわけで、そうすると、欧米の側も、これは本当にロシアというのは警戒するべき国であるということになって、相互不信は出口が見えない状態となってしまっています。
他方、中国との関係では、そういう感情的な問題があまり出てこないということが特徴的です。歴史的には、中国のほうがロシアに一部の領土を奪われた被害者であったわけですし、また、冷戦期には中ソ対立もあった。ですから、ロシアと中国の歴史的な関係というのは、決して単純ではないのですが、現在はアメリカなどを意識した戦略的、便宜的な協力的な関係のほうが優先されている。それから、日中関係などとは違って、歴史問題が簡単にリセットされる関係であると言えます。ただ、脇から見ていて非常に不思議だなと思うのは、ロシアはとにかく欧米中心の世界秩序というものを嫌っているけれども、ではもし、将来、中国中心の世界秩序ができたら、ロシアは必然的にジュニアパートナーになってしまう。そのことをどう考えているのかということは、ロシアの中でもそういう議論をする人がいないわけではないのですが、話題になることは非常に少ないという状態です。
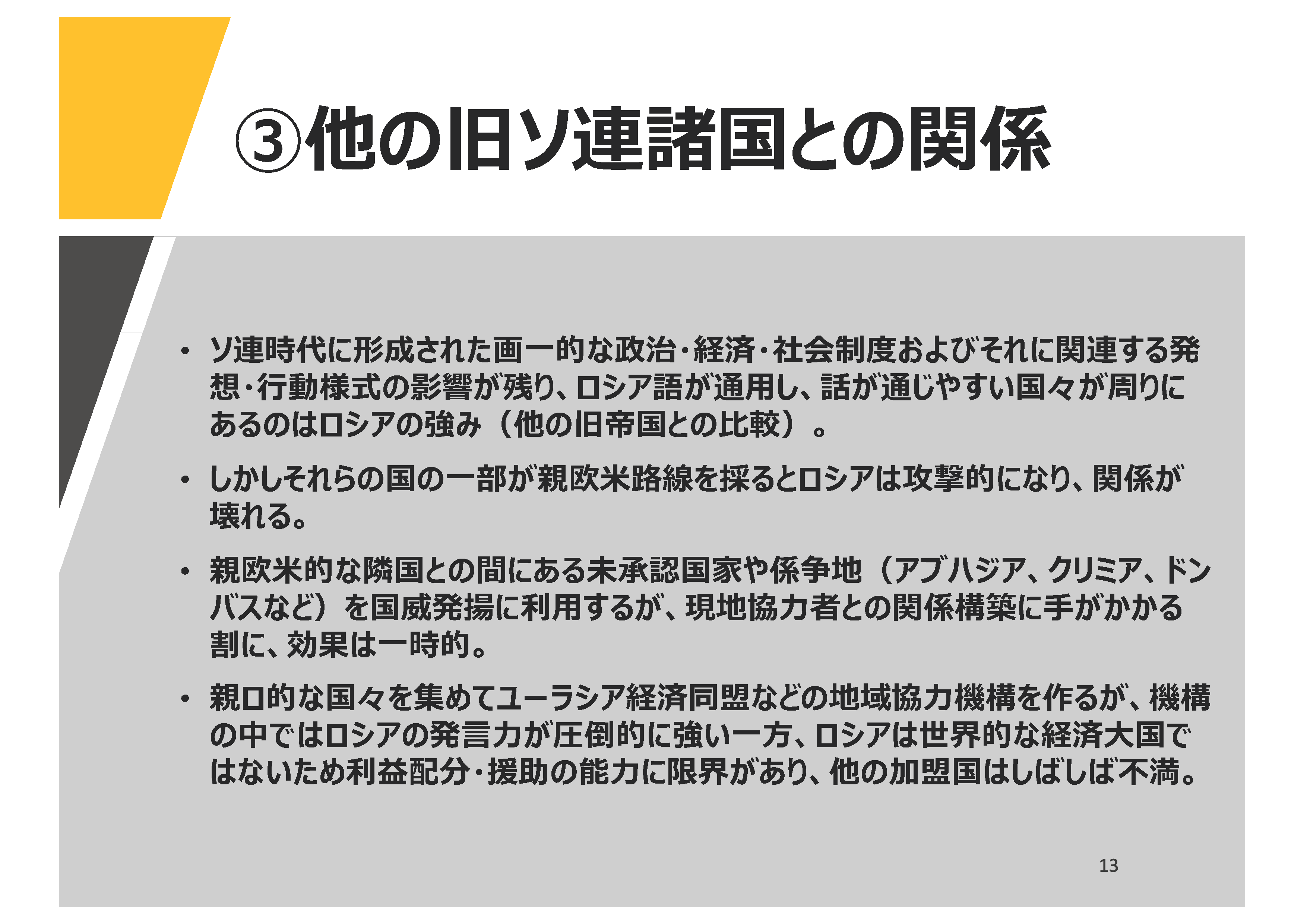
だから、ロシア以外の旧ソ連諸国との関係において、帝国的な問題がどういうふうに現れるかということですが、ソ連という国は、非常に画一的な政治経済、社会制度を構築し、それに関する行動様式とか発想も、全国で共有されていた。分かりやすいところで言えば、非常に官僚主義的な制度がある一方で、その脇には、コネの濃厚な行動様式が張り付いていたというようなことは、全国に共通していたわけですし、それから、ロシア語も広い範囲に普及したということで、そういったことの影響は今も残っていますから、話が通じやすい国が周りにあるというのは、ロシアの強みだと思います。旧帝国の中心ないし宗主国と、旧植民地ないし周辺の国々の関係というのは、日本では、すぐに日本と韓国の関係などが想起されて、帝国が与えた被害に対する旧植民地側の反発というものが意識されがちですが、日本の場合も、例えば、台湾との関係は韓国との関係とは全然違いますし、イギリス帝国の旧植民地、あるいは、フランスの旧植民地と本国の関係というのも、対立はあるけれども、実は相当、親英的、親仏的な旧植民地の国々は多いわけですね。
それから、旧植民地、あるいは旧周辺の国々と話が通じやすいという現象は、決してロシア特殊のものではないのですが、ただ、イギリスやフランスが海外の植民地を持っていたのに対し、ロシアは大陸帝国として、周辺に植民地や、それに準ずる地域を持っていましたから、地政学的に、この周辺の国々の存在というのは、ロシアにとって強みであると言って良いと思います。ただ、問題は、旧ソ連諸国の中でも、まずバルト 3 国の場合は、遅れてソ連に併合というか、強制的に組み入れられたので、そもそも自分たちがソ連に統治されたのは非合法であって、われわれは、それ以前の独立国から連続している国々である、旧ソ連諸国ではないと言っています。それ以外の旧ソ連西部にも、ウクライナをはじめとして、ロシアに対して非常に複雑な感情を持っている国々があるわけですね。そういった国が親欧米路線をとると、ロシアは非常に攻撃的になって、関係が壊れるというのが特にウクライナとグルジア(ジョージア)の問題だったのです。
そういった国との関係では、地理的にその間にある、あるいは、必ずしも地理的に間ではないですが、ロシアと密接な関係にある地域が、未承認国家、あるいは係争地となっていて、それをロシアが国威発揚のた めに利用するということがグルジア紛争のときにもあったし、ウクライナ紛争のときにもあって、今でも続いているわけですね。ただ、具体的にはアブハジアとか、クリミアとか、ドンバスといった地域の人々も、それぞれの主張を持っていますから、例えば、アブハジアは、時にはロシアのかいらい国家と見られるときがありますが、実は相当、独自路線を歩んでいるところですし、それから、クリミアでは、クリミア・タタール人をロシアが味方につけるのに相当苦労しているということであるとか、ドンバスでは、ロシアの協力者となった人たちが、やくざ者的な人たちで問題が絶えないとか、そういう現地協力者、いわゆるコラボレーターとの関係構築に非常に手がかかっている。しかし、そういった地域を使うことで、ロシアが国威を発揚できるというのは、クリミアの場合は、数年持ちましたけれども、場合によっては、ほんの一時的な現象になってしまうというところがあります。
それから、親ロ的な国々。これは中央アジアの多くの国がまさにそうなのですが、そういった国々を集めてユーラシア経済同盟などの地域協力機構をロシアはつくりますが、その機構の中ではロシアの発言力が圧倒的に強い。しかし、他方で、ロシアは経済的には、決して世界的な経済大国ではないから、周りに与えられる利益も少ないということで、他の加盟国がしばしば不満を持つという、言ってみれば、中途半端な帝国的な存在になっているということがあります。
帝国論から見る世界秩序の変化
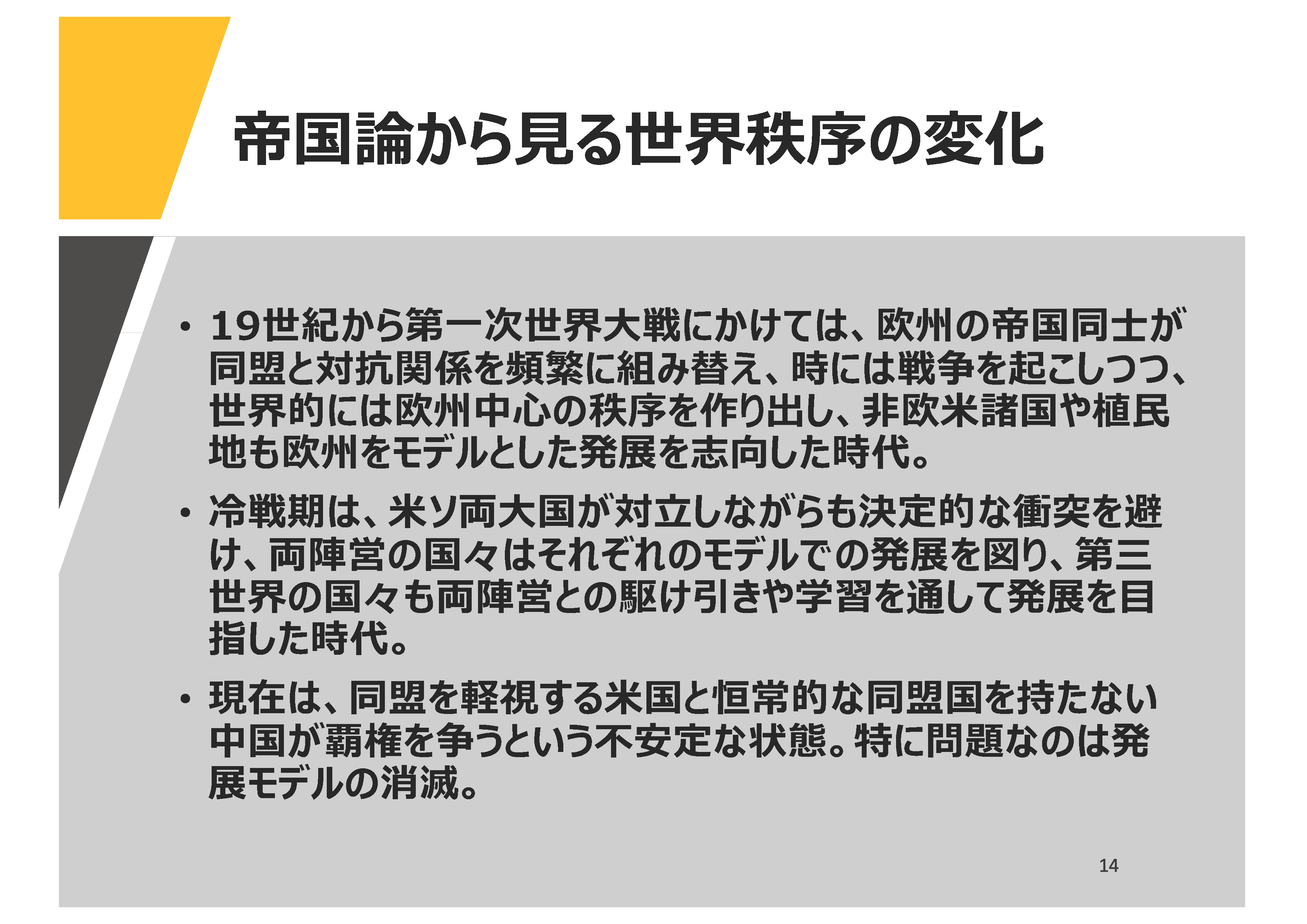
最後の二つのスライドになりますが、現在、世界秩序が大きく変わっている、あるいは、変わりつつある、変わろうとしている中で、帝国論というものをどういうふうに使って見ていくかということですが、まず、長いタイムスパンで見ると、19 世紀、20 世紀、それから現在における帝国的な世界秩序というものは、よく見ると大きく性格の異なる面があります。19 世紀から 20 世紀初めにかけては、ヨーロッパにいくつもの帝国があって、同盟関係と対抗関係を頻繁に組み替えて、時には戦争を起こしていたけれども、世界的にはヨーロッパ中心の秩序をつくるということで利益を共有し、非欧米諸国や植民地も、ヨーロッパをモデルとした発展を志向していったと大まかには言えると思います。
その後、二つの大戦とその間の戦間期いう移行期を経て、冷戦期には米ソ両大国が対立しながらも、決定的な衝突は避ける。その中で両陣営、資本主義陣営と社会主義陣営のそれぞれの国は、それぞれのモデルで発展を図る。第三世界の国々も、両陣営との駆け引きや、学習を通して発展を目指したと言えると思います。現在の国際関係の特徴は、そういった同盟とか陣営というものが、かなり形が崩れてきているということで、アメリカは、いくつもの強い同盟の中心だったはずなのですが、今、それを自ら軽視している。中国は、いろいろな国と関係を構築しようとしていますが、恒常的な同盟国はない。その二つの国が覇権を争っているという不安定な状態です。これは、国家間の関係として不安定であるというだけではなく、世界のいろいろな国々が模範とするような、発展モデルとなる国がなくなってしまっているのではないかということが特に重要ではないかと思います。
その問題が、 今、新型コロナ対応で、まさに現れているわけで、新型コロナは中国発であると同時に、欧米で一番猛威をふるい、それを抑え込むのに非常に苦労しているということで、そこにはもちろん、いろいろな問題、要因がありますが、欧米諸国の社会システム、政治システムの欠陥があることは否定できないわけで、欧米の国際的な威信が更に低下していく。中国の権威主義的な手法が、相対的には説得力を残念ながら増しつつありますが、ただ、中国そのものの体制は共産党という 20 世紀の遺物を核としていて、到底、いろいろな国々が、普遍的なモデルとして受け入れられるものではありません。それから、そもそも大国が常に有利であるということ自体が疑問に付される状態になっていて、新型コロナ対応では、東アジアで言えば台湾が一番うまくいっている。ヨーロッパではスロベニアが一番先に流行終息宣言をしたということで、合理的な政策をとれば、むしろ小さい国のほうが、こういうときの危機対応は成功させやす い。ただ、小国の中でも特に経済的に弱い国は、これから深刻になっていく、経済危機の対応が難しいということで、これから大国が中小国への影響力強化を競って、さらに競争を強めていくのか、それとも、大国自体にそのような余裕がなくなっていくのかという分かれ道にあるのではないかと思います。
世界秩序の行方
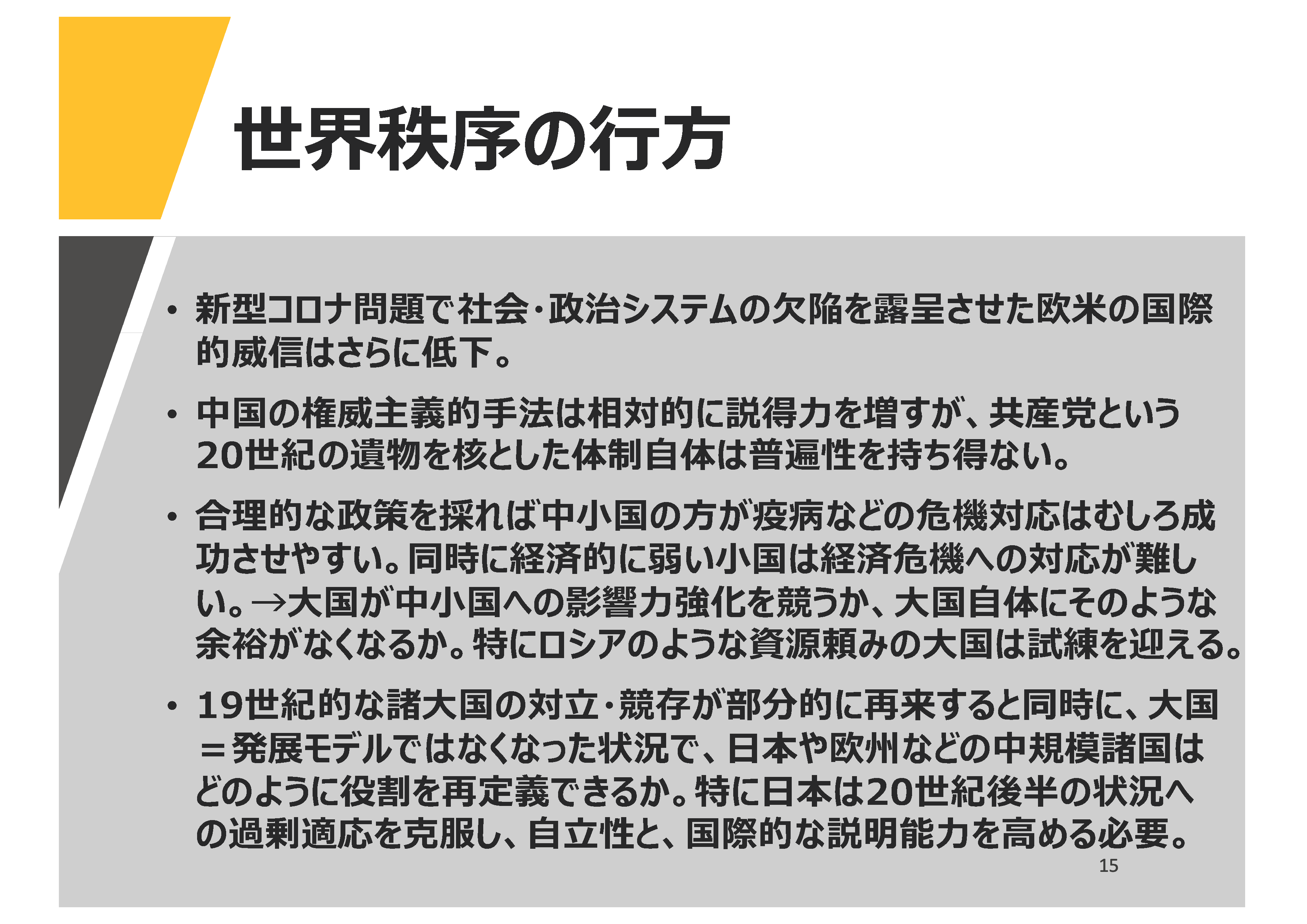
特にロシアは、これまで石油、ガスに大きく依存しており、その資源価格も低下している中で、2010 年代に既に経済的には 2000 年代に比べて余裕がなくなっていく中で、しかし、軍事力を背景として、世界的な存在感を維持したわけですが、それが、これから本当にやり続けることができるのかというのは大きな問題になると思います。現在の、あるいは、これからの世界秩序というものは、冷戦時代的なものでは全くないはずで、部分的には 19 世紀的な、いろいろな大国が対立しつつ共存するということであろうと思うのですが、しかし、同時に大国イコール発展モデルではなくなってしまったという状況で、それ以外の国々がどういうふうに振る舞っていくかということが問われている状況だと思います。
特に日本やヨーロッパなどの中規模の諸国が、どういうふうに役割を再定義できるかというのが重要な問題です。日本は、冷戦期、特に 1960 年代、70 年代ぐらいの状況に非常によく適応して、社会、経済を発展させてきた国ですが、それ故に、21 世紀の状況への対応が遅れがちである。国際関係について言えば、いつまでもアメリカ依存の発想が抜けないという中で、どういう構図になるかはまだ見えないけれども、とにか く、どこかを唯一のトップとして頼りとするのではなく、いろいろな国が対立、共存していく中で、より自立性を高め、それから、国際的な発信能力、説明能力をどう高めていくのかということが、日本のような国にとっては特に重要ではないかというふうに思っております。少々長くなってしまいましたが、以上で私からのお話は終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
脚注
1: 第二回:ユーラシア近代帝国と現代世界~「比較帝国史から見たユーラシア諸国の国制・民族問題」 第三回:「権威主義の進化、民主主義の危機」 原稿が整い次第公開予定。